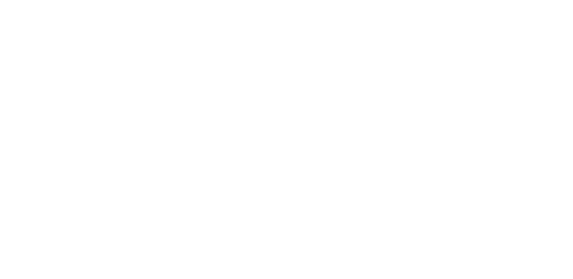MAGIS Stanley Chair ── 静かなる映画的構造美
イタリアのデザインブランドMAGIS(マジス)が発表した「Stanley(スタンレー)」は、一見するとシンプルな折りたたみチェア──いわゆる“ディレクターズチェア”である。だが、この椅子はただのアウトドア用家具ではない。デザインを手がけたのは、現代デザイン界の巨匠、フィリップ・スタルク。彼はこの椅子に、見た目の軽快さとは裏腹に、デザイン史や映画美学を内包するような深みを宿らせている。
その名「Stanley」は、椅子の構造やスタイルから連想される“ディレクターズチェア”の系譜に由来していると同時に、どこかでスタンリー・キューブリックの名前を意識させる。実際、フィリップ・スタルクのプロジェクトはしばしば映画的な演出を漂わせるが、このチェアも例外ではない。
監督の椅子、という寓意
「Stanley」は、従来のX型の折りたたみ構造を再構成し、シングル構造の交差脚へと変容させている。この“骨組みの再編集”は、あたかも映画編集のようだ。フィルムの時間を切り貼りし、新たな構成を作るように、椅子の構造要素を解体・再構築しているのである。
こうした“モダンな監督椅子”の姿は、キューブリック作品に見られる「秩序の中の違和感」「シンメトリーと狂気の共存」をどこか思わせる。たとえば『時計じかけのオレンジ』で描かれた近未来のインテリアや、『2001年宇宙の旅』の宇宙船内装に漂う冷たさと構造美は、フィリップ・スタルクの作風と不思議に共鳴する。
このStanleyチェアは、決して奇をてらったフォルムではない。しかしその“静けさ”は、キューブリック映画における広角で捉えられた無人の空間──美術館のような部屋、無重力空間、精神病院の白い廊下──に通じる緊張感を帯びている。清潔で整然としているが、どこか人間性のゆらぎを内包しているような佇まい。それはまさにスタルクとキューブリック、二人のクリエイターに共通する「デザインする沈黙」とも言うべき美学なのかもしれない。
工業製品としての詩情
素材構成にも注目したい。Stanleyは、ガラス繊維強化ポリプロピレンという現代的な合成素材をベースにしながら、背座部分には耐候性に優れたPlastitexファブリックを使用。この選択は、「屋外でも使用可能だが、屋外専用ではない」という中間的な性格を与えている。つまり、自然と人工、内と外、公共と私的な空間を横断する“椅子のモビリティ”が込められているのだ。
これはキューブリックのカメラが持つ視点にも似ている。人間的な感情から引き剥がされたような、冷たく、しかし正確な視線。無人の部屋や通路を長回しで撮影するシーンのように、Stanleyもまた、誰かが腰かける前の“無人状態”で最も魅力を放っているようにすら感じる。
さらに、折りたたみ式という機能性は、現代の都市生活者が持つ「柔軟さ」「仮設性」にも対応する。使いたいときに開き、不要になればたたんで壁際へ移す──この流動性は、時間と空間が絶えず変化する今日の働き方や暮らしに見事にマッチしている。そしてそれは、キューブリックが描いた未来世界の“可変的インテリア”と重なるところがある。

スタルクが椅子に仕掛けた映画的装置
Stanleyチェアは、建築でもなくアートでもない、明確に“道具”として設計された椅子だが、そのたたずまいはどこか“装置”的である。使われていないときですら、そこにある意味が立ち上がってくる。これは、キューブリック映画の美術セットが単なる背景ではなく、物語そのものを構成する要素になっていたのと同様だ。
とりわけ、フィリップ・スタルクが家具に求めるのは「人と環境をつなぐインターフェース」としての機能性と詩性の両立だ。Stanleyはその点で極めて成功している。構造美が語りすぎず、しかし沈黙しすぎない。空間の中で一歩下がりながら、全体の物語性を支える。これもまた、映画における優れた“脇役”のような存在だ。
Stanley という椅子の余白
MAGIS Stanleyは、ただの折りたたみチェアではない。それは、静かなる映画的装置であり、ミニマルな彫刻であり、移ろいやすい現代の暮らしに寄り添う詩的なプロダクトだ。フィリップ・スタルクは、この椅子に機能美と知的ユーモアを込め、さりげなく現代生活を映し出してみせた。
スタンリー・キューブリックがその世界で語ったように、完璧な美とは、説明されるものではなく“感じ取られるもの”である。Stanleyという名の椅子もまた、使われない空間の片隅で、誰かに座られる瞬間を静かに待っている。